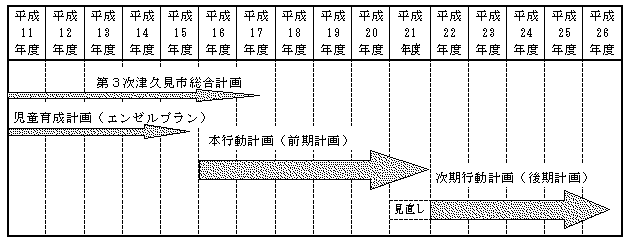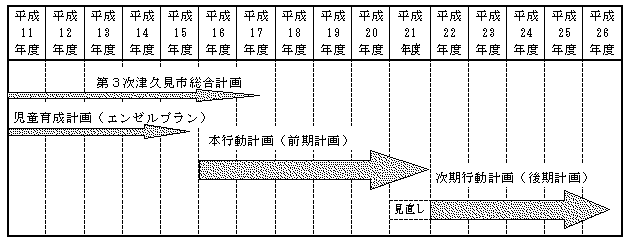|
【要請レポート】
| 次世代育成支援・地域行動計画(先行策定市)の取り組み |
大分県本部/津久見市職労 中津留和子・川野 明寿
|
【市町村名】 津 久 見 市
|
人 口
|
保 育 所
|
幼 稚 園
|
|
総 人 口
|
児童数
(うち就学前児童数) |
か所数
|
定員数
|
か所数
|
定員数
|
|
23,121人
|
3,371人
(924人)
|
3か所
|
241人
|
7か所
|
700人
|
<市町村の概況及び特色>
津久見市は、大分県の東南部に位置し、みかんとセメント、温暖な気候と山・海の幸に恵まれた自然にあふれたまちです。
この恵まれた自然の恩恵を頂きながら、「生涯を託せる津久見づくり」を基本理念に住みよいまちづくりをめざしています。
21世紀を迎え、待望の東九州自動車道や津久見湾の埋立整備も完成し、これらを契機に、「ひと、モノ、心の交流とふれあいのまちづくり」をキーワードに、健康で、明るい市民生活を送ることができるまちづくりを推進しています。
<子育て支援施策の現状>
津久見市では、少子化対策を市政の最重要課題の一つとして位置付け、平成11年3月、母子保健サービスの充実や児童健全育成の推進などを主な内容とした「母子保健計画・児童育成計画(エンゼルプラン)」を策定し、子どもたちが健やかに育ち、喜びや楽しみをもって、子どもを生み育てる環境づくりを推進してきました。
さらに、多様化する子育てニーズに対処すべく平成14年4月福祉事務所内に「子育て支援係(保育士3人、事務職2人)」を新設。子育てに関する相談や育児サークルの育成支援業務など児童部門の統括的部署として、市民サイドに立った子育て支援事業を展開中です。
<子育て支援施策の課題、展望>
子育て支援施策の課題として、子育てに対する意識の多様化、核家族化の進行に伴う家族形態の変化や、近隣との人間関係の希薄化による、家庭や地域における子育て支援機能の低下によるさまざまな問題等、子どもを取巻く環境は大きく変化し続けている中で、各種事業の内容の見直しを含め、市民ニーズに沿った適応性のある事業の選択が必要です。
これらの課題やニーズを的確に判断すべき次世代育成支援・地域行動計画の策定を契機として、本計画に沿った関係機関の連携と事業の展開を図りつつ津久見市がこれまで進めてきた子育て支援を一層充実し、子育てに夢や喜びや楽しみが感じられるまちづくりを目指していきたいと思います。
1. つくみ子ども育成支援行動計画 <概要>
(1) 行動計画策定の趣旨
子どもは「未来の夢」、「次代の希望」です。ところが近年、我が国の合計特殊出生率は一貫して低下し続け、平成14年には「1.32」と史上最低記録を更新しており、「少子化問題」は早急に取り組まなければならない最も重要な課題です。
本市では、少子化対策を市政の最重要課題の一つとして位置づけ、平成11年3月、母子保健サービスの充実や保育・児童健全育成の推進などを主な内容とした「母子保健計画・児童育成計画(エンゼルプラン)」の策定や、平成14年4月に福祉事務所内に「子育て支援係」を新設するなど、子どもたちが健やかに生まれ育つための環境づくりを推進してきました。
しかしながら、核家族化の進行、就労環境の変化、近隣関係の希薄化などを背景に、家庭や地域における子育て力の低下は著しく、親の育児負担感の増大などが生じ、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化するとともに、依然として少子化に歯止めがかからない状況が続いています。
こうした中、国においては、少子化の流れを変えるため、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、平成17年度から10年間、地方公共団体及び企業が集中的・計画的な取り組みを促進する「行動計画」の策定が義務付けられました。
本市では、全国の先行策定モデル(全国53市町村)として指定を受け、これまで進めてきた子育て支援施策や国の「行動計画策定指針」等を踏まえた、次世代育成支援地域行動計画の策定に取り組み、掲げられた理念を具現化するため、計画的に推進していく「つくみ子ども育成支援行動計画」として策定するものです。
(2) 行動計画の性格・位置づけ
本行動計画は、「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)第8条第1項に基づく市町村行動計画として位置し、すべての子どもと家庭を対象として、津久見市が今後進めていく子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めたものです。
また、この行動計画は、「生涯を託せる津久見づくり」を基本理念とする「第3次津久見市総合計画」(平成8年3月策定)を上位計画とし、各種関連計画との整合性をもったものとして定めています。
また、本行動計画の実施に当たっては、行政のみならず、家庭や地域、保育所、幼稚園、学校、企業等が、次世代育成支援(次代を担う子どもやこれを育成する家庭を社会全体で支援すること)の視点に立ち、一体的な施策の推進を図るものです。
(3) 行動計画策定において重視すべき視点
本行動計画策定にあたっては、以下に示す4つの視点に重視しました。
① 子どもの視点
子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次代の社会を担う子どもの幸せを第一に考え、子どもたちの意見を取り入れること。
② すべての子どもと家庭への支援の視点
子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、すべての子どもと家庭への支援という視点から策定すること。
③ 地域における社会資源の効果的な活用の視点
子育てに関する活動を行うNPO、子育てサークル、母親クラブ、子ども会、主任児童委員、区、児童館、公民館をはじめとする様々な地域の社会資源を十分かつ効果的に活用することと、本市の自然環境を効果的に活用する取り組み。
④ 地域特性の視点
本市の地域の特性を生かした子育て環境づくりや、離島・半島部までいきわたる子育て支援施策の取り組み。
(4) 行動計画の期間
「次世代育成支援対策推進法」に基づく市町村行動計画では、平成17年度からの5年間を第1期とし(前期計画)、前期計画の見直しを平成21年度に行った上で、平成22年度からの5年間の後期計画を定めることとしています。
しかし、本市においては、先行策定市町村(53市町村)のひとつとして1年先行して計画策定に取り組んできたことと、子育て支援に関する新たな取り組みを少しでも早く展開するために、平成16年度を初年度とする前期6年間の計画を策定しました。
さらに前期6年間の計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行っていくこととします。
|