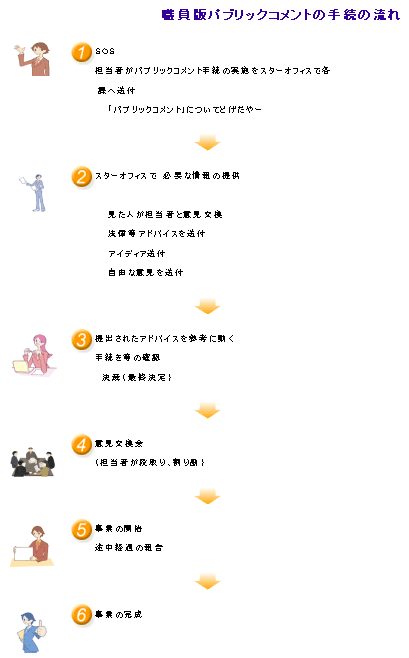【自主レポート】 |
第32回北海道自治研集会 第Ⅰ-①分科会 市民と公共サービスの協働 |
|
1. はじめに みなさんは、「市役所が好きですか?」「市役所で働く仲間が好きですか?」と聞かれたとき、どう答えますか。「大好きです!!」と答える人、多ければ嬉しいのですが……残念ながらあまり多くは期待できないように思います。 では、どうすれば好きになれるのか、誇りがもてるのか。 今も十分楽しいよ! という人は、今よりもっと楽しくなるように、そうでない人は、今より少しでも楽しくなるように、一緒に考えていただければと思います。 |
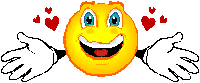
|
2. ステップ1:自分自身のこととして考える 市役所を好きになる第一歩は、市役所のこと、特にそこで行われている事業をよく知ることです。これは口で言うのは簡単なのですが、なにしろ「ゆりかごから墓場まで」の市役所ですから、業務の内容はとてつもなく幅広い。そんな市役所の仕事を、隅から隅まで知り尽くすなんてことは、とても大変なことです。ただでさえ業務量も増えて、自分の仕事を覚えるだけで精一杯なのに……と思われる方も多いでしょう。 突然ですが、ここで問題です。 「ごみ減量貯金箱制度」 これらは、「市報松江4月号」の掲載された「平成20年度 市長施政方針」で紹介された事業の一部です。 ついでに紹介しておくと、タイトルにある「ひとごとからわがことへ」は、2006年度策定の松江市人権施策推進基本方針の基本理念の一つで、元々は、『差別はされる側ではなくする側の問題であることから、する側にいる自分達の意識から変えていきましょう』という活動する市民グループの活動テーマを活用させてもらったものです。もう一つ、『差別される人の痛みを自分自身の痛みとして問題を考える』という意味もあると私は理解しているのですが、「人権」を考えるときだけでなく、日常のいろいろな場面で、自分自身に言い聞かせたい言葉だと思います。 |
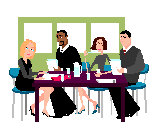 |
3. ステップ2:つながりをつくる ~仲間づくりからはじめよう~ 市役所を好きになるためには、もうひとつ、仲間をたくさんつくることが大切です。これは、とても簡単な方程式です。 仲間が一人であれば、応援したい事業も一つかもしれませんが、二人いたら応援したい事業も二つ。十人いたら十、百人いたら百。仲間がたくさんいればいるだけ、応援したい事業がふえ、いつのまにか市役所大好き方程式ができあがってるという訳なんです。 |
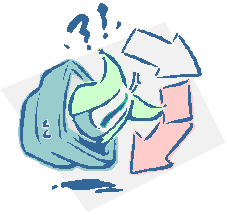
|
4. ステップ3:制度を楽しみ、楽しい組織を! 何かの事業を行おうとするとき、「担当は君だから」と言われたのはわかるけど、具体的に何から始めたらいいの? ……という経験ありませんか。 |
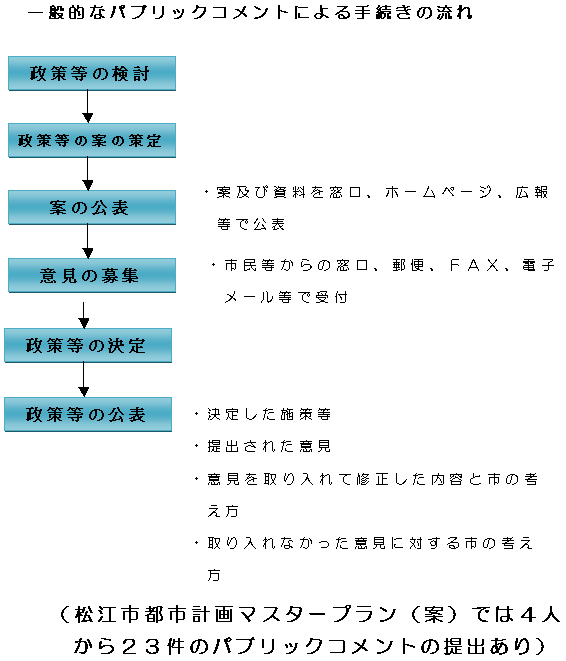
最近は、様々な計画を策定される際には、ほぼ必ず使われている手法ですから、実施された経験をおもちの方も多いと思います。 今回、「職員版パブリック・コメント制度」を提案するにあたって、14人の方に緊急アンケートを実施しました。 【回答】 自分の今の業務以外のことについて自由にコメントすることが、今まで以上に当たり前となるための作戦、それを面倒くさがらない体質、コメントしたがゆえに仕事が増えてしまうことへの不満の払拭など制度整備の前に何を露払いすべきか、そのために何を行動すべきかを考えることが重要では……と思います。 ☆ 返事、遅くなってすみませんm(_ _)m ★ なかなかよい提案だと思います。さらに単なる否定、批判の場にならないよう意見には必ず前向きな提案も加えるなどのルール作りがされるといいのではと思います! ☆ お疲れ様です。事業について、あらゆる課の人が意見できるということでしょうか? 今の仕事ではあまりピンときませんが、新しい事業を進める上で、多方面から、多くの職員の知識、意見、経験が生かすことができそうで、良いと思います。デメリットはある程度の期間がかかってしまうこと、どこまで参考にして、しばりはどこまであるか等位置付けをはっきりする必要があると思います(^_^)っ ★ 確かに。「このプラン、あの部署にちゃんと確かめて作ったのかなぁ……」的な出来事は多いですよねぇ。 ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。 |
|
|