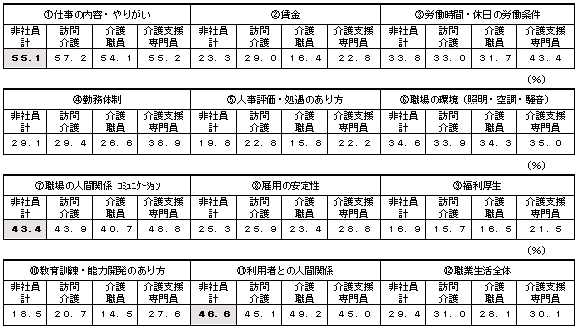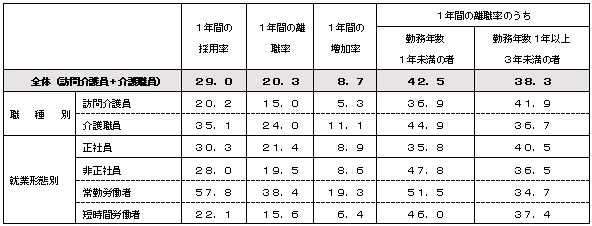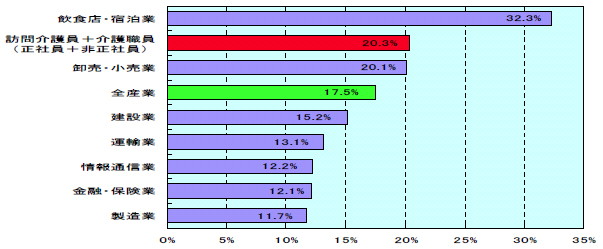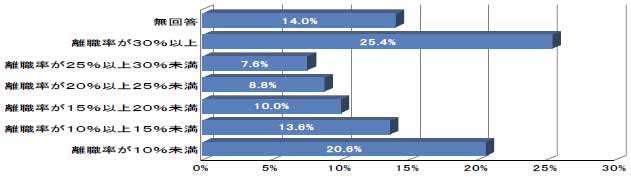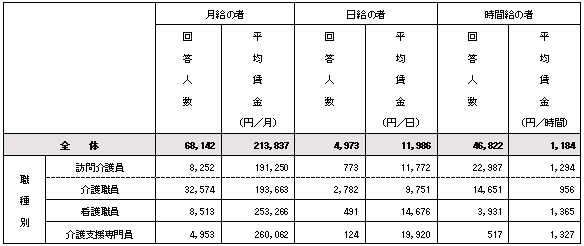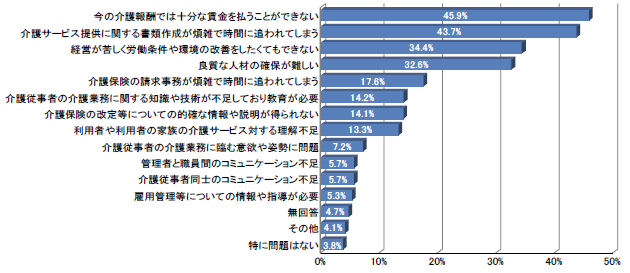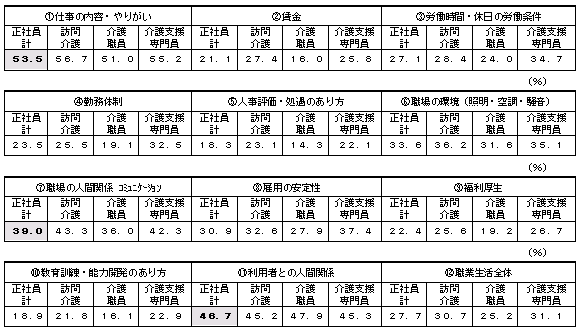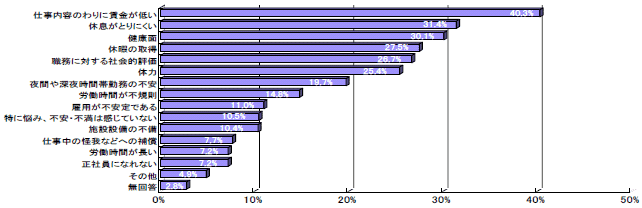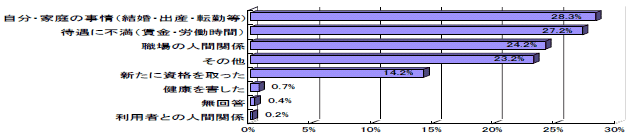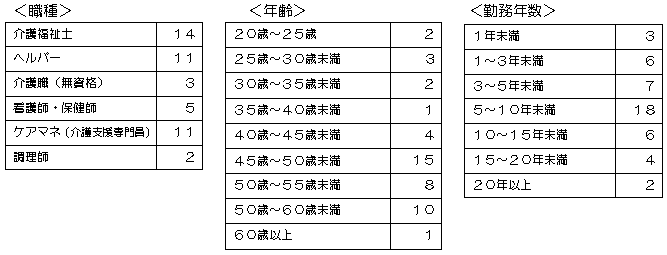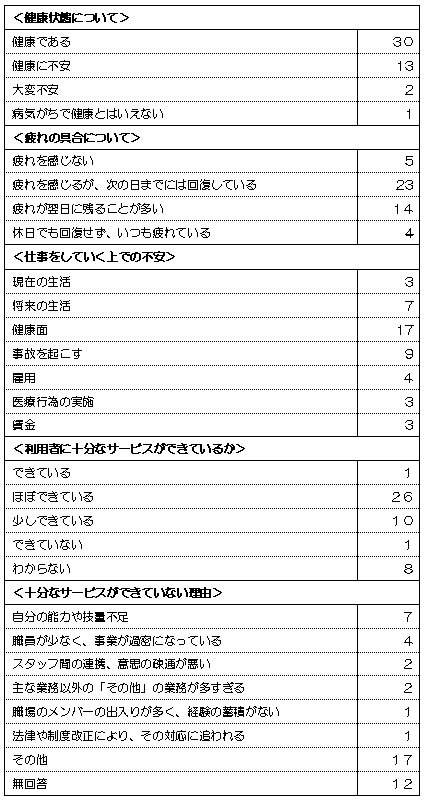健康状態では、健康に不安を持つ職員が3割、疲れを感じている職員にいたっては9割いることがわかりました。仕事をしていく上での不安は、健康面が4割、雇用・賃金が2割となっています。
サービスについては、できていると答えた職員が6割近くいる一方で、できていない理由として事業の過密や業務量が多いという実態もありました。
<あなたが福祉の仕事をやって良かったと思うことは?>
・利用者さんから、喜ばれたり、楽しかったと言葉を言われたり、感謝された時。
・人と接することが好きなので、充実感がある。
・状態の悪かった高齢者が改善し、自立した生活を送れるようになった時など。
<どうしたら健康な生活、明るい職場になることがでるか?>
・信頼でき、意見が言い合える職場。
・安心と自信が得られる職場環境。
・職員同士のコミュニケーションを密にとり、思いやりの心を持てばよいのではと思う。
<介護・福祉関係の労働や利用者の処遇改善に向けた国・自治体など行政への意見>
・福祉の現場は9K(「きつい」「汚い」「危険」「休暇が取れない」「規則が厳しい」「化粧がのらない」「薬に頼って生きている」「婚期が遅い」「給料が安い」)だと知ってほしい。
・介護福祉関係に関わる者が、全体的に底上げをし、より専門性を高められるような教育を施してほしい。
・精神的にも、体力的にもかなり重労働です。もっと賃金を上げてほしい。
・高齢者の行き場が圧倒的に少ない。国は現状を分かっていない。
<労働組合への率直な意見、要望>
・残業の少ない職場。
・各休暇がもっとほしい。
・賃金の不公平を是正していただきたい。
介護労働者は、過酷な労働条件、低賃金や健康・生計などの不安を抱えながらも、仕事に対して誇りと熱意、やりがいを持って、現在の社会を築き上げられた高齢者と寄り添いながら、高齢者のゆとりある生活を援助できるよう働いています。
少子高齢化はさらに進んでいきます。介護は誰もがいつか直面する問題です。介護労働者の処遇改善と介護サービス事業の経営安定化に向けて、早急に具体的な対策を講じなければならないと考えます。
3. 介護従事者の処遇改善と人材確保 国の動向
国の動きとしては、2008年4月25日に「介護従事者処遇改善法案」(人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案)が衆院本会議で可決されました。
介護職員の人材確保をめぐっては、民主党が介護報酬を上乗せして職員の給与引き上げを目指す「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を先に提出していました。この法案では、平均賃金の金額が一定以上となる見込の認定事業所に対して、介護報酬を3%加算することとしています。全事業所が認定事業所となった場合、2005年度の介護費用総額6兆円からみて介護報酬の3%すなわち約1,800億円の介護報酬増額となります。この増額分をすべて人件費に充当すれば、介護労働者約80万人(常勤換算)に対して、月額2万円程度の賃金引上げが可能になるとしています。現時点では、認定事業所となる事業所は全体の約50%と考えており、財源規模は900億円と推計されています。
この財源は全額、税財源とし、介護保険料の引き上げはしないとしています。また、介護報酬の加算分は介護保険から10割給付にすることにより、認可事業所における利用負担額をアップさせないこととしています。今回、民主党はその法案を取り下げましたが、来年4月の介護報酬改定を視野に入れ全会派が共同提案する形で自民党案が可決されています。
しかしながら、その法案条文には「介護を担う優れた人材の確保を図るため、2009年4月1日までに介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策のあり方について検討を加え、必要があると認める時はその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という一文のみで、具体性に乏しく抽象的な法案という指摘もあります。また、介護現場の窮状を改善するには、中身よりも法律の制定を優先させたという見方もあります。
5月16日の参院本会議では、インドネシア人の看護師や介護福祉士の受け入れを柱としたインドネシアの経済連携協定(EPA)が承認され、7月から今後2年間で、インドネシアで一定の実務経験がある看護師400人と介護福祉士600人を受け入れることとしています。両国の仲介機関を通じて、来日希望者と求人施設とのマッチングが行われ、来日したインドネシア人は半年間、日本語等の研修を受けた後、受け入れ先の病院や施設で看護師の助手や介護職員として働くことになります。但し、ビザの有効期間中(看護師3年、介護福祉士4年)に日本の国家試験に合格しなければ帰国しなければならないということや、受け入れ施設側の手数料負担が一人当たり60万円などの条件があります。(2007年度 看護師国家試験合格者 46,342人 合格率90.3% 、介護福祉士国家試験合格者 145,946人 合格率50.4%)
この受け入れについては、人手不足にあえぐ介護業界からは歓迎の声も上がっていますが、厚生労働省は、あくまでも「人手不足対策ではなく、労働市場の開放を求めるインドネシア側の要求に基づき、EPAで受け入れを盛り込んだことに対応した」としています。また、日本看護協会や日本介護福祉士会は門戸開放には反対しています。国内の介護労働力を確保するには、賃金をはじめとする処遇向上と潜在的な資格保有者の雇用促進・職場復帰の対策が優先であるとしています。
4. 今後の課題の整理
まず、第一に取り組むべきことは、介護労働者の賃金等の処遇の改善であると考えます。
そのためには、来年4月の介護報酬引上げは必須でありますが、介護報酬には訪問介護や居宅介護支援などのサービス事業ごとに、具体的に「単位」が定められ、人件費や賃料の地域格差もあることを考慮して、上乗せの「地域加算」が設けられています。したがって、それらの介護報酬水準が適正に反映されるよう、様々な角度から具体的に分析していく必要があると考えます。その分析に基づき、国も、民主党が当初提起した積極的、かつ実効性のある施策を講じなければならないと考えます。介護報酬は保険料と税金による政府の介護保険で賄われていますので、国民の合意に基づく負担の見直しも必要であると考えます。
次に、働いている介護職の定着率向上に向けては、賃金水準だけではなく、仕事の評価(人事評価・処遇)についても改善を図る必要があります。今後、介護サービスに関する需要が増える中で、法案の条文にあるように「介護を担う優れた人材の確保」をしていくためには、専門職として介護労働者の地位・社会的評価を確立させていかなればならないと考えます。
さらに、就業形態や能力に応じた人材配置、能力開発を促進する適正な人事労務管理を進めていく必要があると考えます。
20万人いる「潜在有資格者」の活用については、実質的に就労可能な「潜在有資格者」の実態を把握していくことが先決であると考えます。資格を持ちながらその職に就いていないわけですから、そのうえで、具体的な対策を行わなければならないと考えます。
外国人介護労働者の受け入れについては、十分に議論される必要があると考えます。「人員」の確保という点では、ひとつの選択肢であると言えますが、利用者や職場でのコミュニケーション・言葉や文化の違いなど様々な問題があります。介護は利用者の生命・生活・人生に関わる仕事です。
利用者の尊厳を守るケアを行うには、文化・ライフスタイル・習慣などを十分に理解する必要があります。また、受け入れ側も、外国人労働者の文化の違いなどに配慮することが必要であり、今後受け入れのあり方についてはさらなる検討が必要であると考えます。
介護労働力の減少問題は、一過性のものではなく長期的な対策でなければ、さらに進む超高齢化社会を支えていくことはできないと考えます。一部の関係者だけの問題ではなく、国民が理解し自分のものとして考えなければ、本当に充実した「福祉社会」の実現にはならないのではないかと考えます。
5. 組合として求められる対策
組合としては、介護職場で働く労働者の働きがいを高め、質の高いサービスを安定的に提供することができる職場環境の支援を行っていくことが必要であると考えます。具体的には、顕在する賃金格差の是正を強く求め、労働条件の改善や安全衛生体制の促進として、時間外労働の縮減や休暇取得の推進について積極的に取り組んでいく必要があると考えます。
また、職員の定着・能力開発を促進し、専門性やスキル形成を行うため、資格取得や継続的な研修の機会を持つよう要求していくことが必要であると考えます。利用者・介護職双方の可能性を広げる経営・事業戦略、人事管理のあり方について、当局に強く要求していく必要があると考えます。
労使が共に、更に魅力ある職場づくり、利用者に選ばれるサービスを実現することで、職員の労働環境に還元し、さらに利用者・介護職の満足度向上・経営の安定が図れると考えます。 |