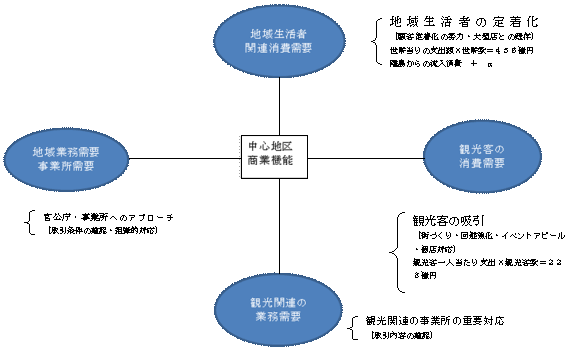(1) 地域消費者(生活者)需用に対応する商業活動
公設市場周辺(中心市街地)は、歴史的に見て八重山地域の政治経済文化の中心であり消費の流入があって、商業の拠点として位置づけられてきた。一部離島の消費の流入も見られる。
石垣市における消費需要額は、世帯当りの消費支出額×世帯数=456億円:2006年/(351億円:1995年)商業統計による推計。それに離島関連の消費が+αとして推計できる。
(2) 観光客の消費需要
観光関連の消費は、観光入り込み数の増加傾向があり、消費の拡大が見られている。
その観光客関連消費額は、観光客一人当たりの支出額×観光客数=228億円:2006年/(135億円:1995年)概算
街ぐるみでの観光消費の対応策の実践が求められるが、統一した実践的な取り組みはまだまだ弱いと思われる。
例えば、市内の事業者にあってはもちろん、商店街においても積極的に商店街内での購入機会を高める努力が必要である。
(3) 地域業務、観光関連事業所業務需要
事業所(公官庁・民間事業所)の中には業務用としての消費単位が大きいものがあり、市外業者からの納品実績が大きいものも考えられ、業務用需要も積極的に意識しての対応が求められる。
これまでの商店街組織活動をみると、これら地域生活者(市民)の生活向上と商業街の活性化を図っていくためには、個店で活動するより共同で行ったほうが効率が良く売上高に高く結びつく。しかし本来の組織活動(通り会、TMO、振興組合等の一体的な活動)である共同事業が不活発である。各通り会が7つあるが、親睦団体の域を出ていない所が多い。大型店のマーケティング力に劣らない商店街活動が求められる。それが商店街再生の原動力となるからである。
3. ハード面の整備と商業集積効果の向上
行政にとって地域の中心の顔である中心市街地をどうやって作っていくのか、魅力あるまちなみ形成は重要な課題である。730交差点を中心とする半径300mの範囲における回遊条件の整備、集積を高めることが求められている。
これらハード面の整備は、商業者自身の努力は当然として、街の顔としての商店街の整備と大型店と商店街の公正な競争が行われる条件の整備を図るという観点から行政の役割が求められる。
都市建設課では、2006年2月に中心市街地地区都市再生整備計画を策定し、以下の事業を展開している。
大目標:ようこそ とぅもーるへ 交流拠点いしがき~海に開かれた交流による都市観光のために~
目標1:海と中心市街地を人の交流を促進する拠点として一体的に形成
目標2:石垣、八重山の地域資源を活用し、「石垣らしさ」を再生
目標3:情報等の充実を図り、観光客、買物客等来街者をもてなす機能の強化
<主要な事業>
① 高質空間形成施設・緑化施設等(基幹事業/中心市街地内道路環境等整備事業 2008~2010年度事業)
② 地域生活基盤施設・広場(基幹事業/中心市街地内道路環境等整備事業:ポケットパーク2008年度整備)
③ 地域創造支援事業(提案事業/あやぱにモール内環境整備事業2007年度整備済み)
④ 地域創造支援事業(提案事業/ゆんたくひろば整備事業:2007年度整備済み)
⑤ まちづくり活動推進事業(提案事業/社会実験:まちづくり活動支援事業)
⑥ 地域生活基盤施設・公開空地(基幹事業/蔵元跡地整備事業:公開空地整備2009年度整備)
⑦ 地域生活基盤施設・情報板(基幹事業/回遊スポット整備事業:2009年度整備)
⑧ 地域創造支援事業(提案事業/景観形成推進事業:2009年度実施:2009年度実施)
⑨ まちづくり活動推進事業(提案事業/回遊スポット整備事業:資料収集・出版:2009年度実施)
⑩ まちづくり活動推進事業(提案事業/まちづくり活動支援事業)
⑪ 地域生活基盤施設・情報板(基幹事業/情報板・案内板整備事業)
⑫ まちづくり活動推進事業(提案事業/回遊マップ整備事業)
⑬ まちづくり活動推進事業(提案事業/まちづくり活動支援事業)
4. 公設市場の活性化による商業集積効果の向上
公設市場は、商店街の中心核としての期待を担って1987年に全面改装されたが、現状は、半地下と1階・2階の一部にテナントの入居があるが、活気の乏しいものとなっている。公設市場は立地・規模的にも中心商店街のマグネットになり得る存在であり「核」としての機能を果たさなければならない施設である。
2002年に市場の日を設定しイベントを実施していたが、予算が乏しいことから現在は休止となっている。通り会を始め再開・復活が求められる。
最近では、観光客の増加により一部では活気を取り戻しているが、那覇市の牧志公設市場のような観光客の関心も高く賑わいのある市場として活気を取り戻すことが期待される。
商工振興課や観光課及び観光協会の事務所の移転により地元市民の流れが期待できる。また、一般の利用者を増やすために展示会場として常に人を呼ぶ施設として有効利用を図り、コミュニィティ施設としての利用ができないかも検討が必要と思われる。
5. 個々の業者の経営努力による商業集積効果の向上
・都市再生整備計画に合わせた店舗・施設の整備を図る。
・商店街組織と連動した販促の強化を図る。(わくわくスタンプ会)
・個店独自の販促活動の実施(ポスティングやDM、新聞情報誌への広告等の活用)
・「経験と勘」に「計数管理」を加えた商店主の経営レベルの向上を図る。
経営管理活動を活発に行うためには、強いリーダーシップが発揮できる仕組みづくりと人材が求められる。そこの代表者(リーダー)に求められる資質として、健康、ビジョン、決断力、実行力、統率力、誠実さなどが重要であり、加えて商業経営に明るい者が望まれる。
6. 空き店舗対策と商業集積効果の向上
2000年と2004年の2度にわたる空き店舗対策事業を商工会が実施をし、15店舗を立ち上げている。その起業者のほとんどが内地から来た若者で占められ、地元人は少数である。県内における商店街においては、多くの事業所は成り立っていないと聞いているが、石垣市においては、健全に営業を続けているところである。
7. 中心市街地活性化に向けての行政の積極的な関与
ハード事業の実施には、莫大な経費、時間、労力が必要となる。商業者自身の自助努力はもちろんであるが、それだけの組織力では賄いきれない。よって、地域の中心の顔をどうするのか、街づくりの「核」となる商業地の問題であることから、市、県、国が街づくり・都市形成としての中心市街地の再生へ向け努力をしていく必要性がある。
8. 石垣市中心市街地活性化へ向けての具体的取り組み
(1) 都市再生整備計画の着実な実施をする。→道路環境の整備やまちづくりセンターの整備により、市民、観光客にとって楽しみのあるまちなか、更には利便性・回遊性を高めるためのハード面の整備を行う。
(2) 石垣港湾計画の方針に「中心市街地へ連絡する緑道・遊歩道等の配置」の実現を図る。
(3) 郊外開発を抑制するための都市計画の運用方針、都市機能の集約、郊外の大規模店舗の立地規制を図る。具体的には、都市計画法に基づく特定用途制限地域指定、地区計画や景観地区の決定、風致地区の指定等が考えられる。
(4) 中心市街地活性化協議会の設立を早急に行う。また、基本計画策定に向け取り組みを進める。
9. 石垣市における経済の循環・流動性の課題
・消費者の最終消費をした資金の流れはどうなっているのか?
・地元資本(企業)はどれだけの資金のストックができているのか?
2006年度における各業種ごとの生産額は、農家の生産所得(約95億円)、漁家の生産所得(約10億円)、建設業公共工事請負額(150億円)、製造加工業品出荷額(119億円)、観光関連収入額(228億円)、公務員等公官庁所得(政府サービス生産者)(203億円)、総計805億円の内、地元に落ちる資金が大型スーパーをはじめ郡外企業(資本)により郡外(市外)へ流出している。それを断ち切るためにはどのような施策が考えられるのか検討を加えていく必要がある。
郊外型の大型スーパーの販売シエアーは、1995年頃は、約60%と見られていた。近年では、おそらく80%強は大型スーパーが占めていると推測される。
入るパイプよりも出て行くパイプが太いと経済の循環は健全には機能しないのではないかと思われる。沖縄経済がザル経済と言われているが、八重山はその縮小版と考えられ、石垣市もザル経済に近い状況にあると思われる。
その外、郡内に専門学校や大学が無いことにより、高校を卒業と同時に沖縄本島や本土へ進学をしていく。一人当たりの送金額を約200万円/年×300人=6億円の資金が郡外へ流出していると考えられる。
最終消費がどこで行われたかがそこの地域経済が活発になるか停滞または衰退していくかの分岐点になる。地元企業が育たない、元気がなくなるそして、当然石垣市への法人税納税額が漸減する。このように、資金の流れ・循環が悪くなると同時に石垣市の企業活動が不活発になり地元経済人が小さくなっていく恐れがないか危惧される。
そのような状況がこれまでと同様に推移していけば、本市の生産者(製造業)をはじめ、あらゆる事業者が伸びていくことができず、おこぼれ程度の資金での経済活動を強いられ経営が沈滞していくことが想像される。その結果石垣市全体の経済の循環・資金の流れが悪化し地元企業・経済活動の衰退が懸念される。 |