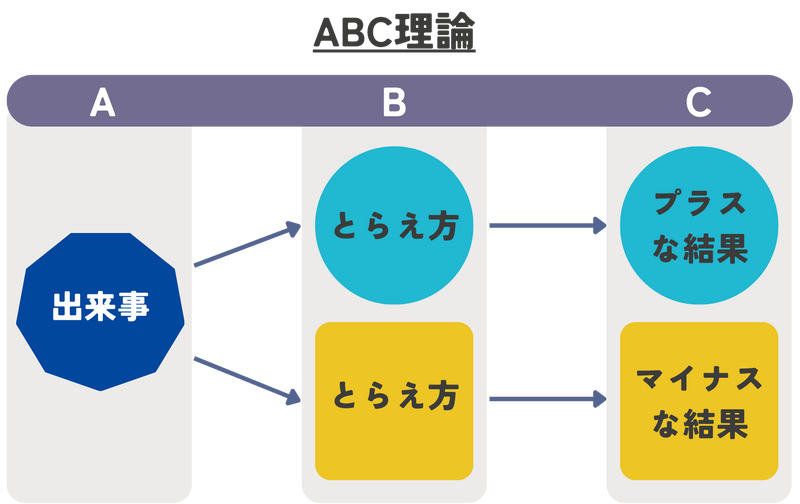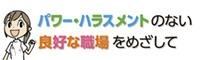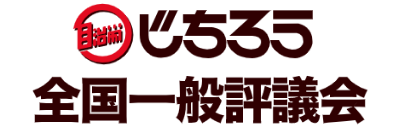2025/04/25

4月25日、総務省は「地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査結果」を公表しました。これを受け、自治労は下記の通り談話を発出しましたので掲載します。(最下段よりWordファイルをダウンロードできます)
総務省「地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査結果」に対する書記長談話
地方公務員を対象としたハラスメント調査が、初めて総務省により実施され、4月25日結果が公表された。
回答者が特定されない方法で調査が実施されたことにより、ハラスメント被害の実態が明らかになったことは意義深いといえるものの、法定されたハラスメント対策の公務職場での実効性が疑われる結果となったことは、多くの組合員が自治体で働いている自治労として深刻に受け止めざるを得ない。
とりわけ、パワハラ防止については、2020年から労働施策総合推進法により雇用管理上の措置を講じる義務があるなかで、過去3年以内にパワハラを受けたと回答した者が15.7%(見聞きした、については38.1%)にのぼっており、うち行為者の上位1位が上司、2位が幹部であることは自治体当局や責任者の認識の低さを露呈したものとして厳しく評価されるべきである。昨今、首長などによるハラスメント被害の報道も後を絶たないが、これらが氷山の一角にすぎないことも明らかになった。
今回の調査では、深刻かつ重大なセクハラ被害についても明らかになった。性的な冗談やからかい、不必要な身体への接触に始まり、性的な内容の情報の流布、性的な関係の強要など犯罪要件を構成するのではないかとも思われる被害者がいること、加えて、被害者の多くが「何をしても解決にならないと思った」「職務上不利益が生じると思った」としていることなど、労働組合として十分対応できてない点があることについて認識する必要がある。
カスハラについては、自治労における調査結果同様、高い割合で被害があることが改めて明らかにされた。過去3年間に、カスタマーハラスメントを受けたこと(受けたと感じた経験)がある者の割合(35.0%)は、民間(10.8%)より高く、カスハラを受けた頻度が、「週に数回(7.1%)」や「ほとんど毎日(2.3%)」という異常な職場実態については、現時点では対策が努力義務にとどまるとしても、早急に対策が講じられなければならない。
パワハラ、セクハラ、マタハラ・パタハラ被害のいずれにも共通する職場の特徴に、コミュニケーションの問題と同レベル程度に「人手が常に不足している」「休暇を取得しづらい」ことがあげられている。多くの職場で人員不足に陥っており職員が疲弊している実態と「休暇を取得しづらい」職場におけるハラスメントの発生割合が高いことが明らかであり、いずれも喫緊の課題として改善にむけた対応が求められる。
相談者のプライバシー保護や不利益取り扱いの禁止、制度周知などハラスメント対策の現在地がいずれも不十分なことも明らかになった。法律を遵守し、率先垂範すべき自治体において「事業主としての雇用管理上の措置義務」を果たすという当たり前のことが当たり前に実施されるよう、ハラスメントの撲滅にむけ自治労として県本部、単組とともに運動を強化していかなければならない。
カスハラ対策については、第217回国会に労働施策総合推進法改正案が提出されており、今後審議入りの見込みとなっている。地方公務員においても離職者の増加や精神疾患を理由とする長期休職者が倍増する中にあって、組合員を守るためにも公務職場の特性に合わせた対策を講じることが急務の課題である。公務も含めたすべての職場でカスハラ対策が実効性を持つこととあわせ、消費者や障害者など利害関係者の意見が反映されること、行政サービスの提供にあたって住民の権利が侵害されることのないよう、バランスが取れた国会議論とその後の具体化を求めていく。自治労はそうした立場で、連合に結集して、法案の可決・成立にむけて、国会・省庁対策を強力に進めていく。